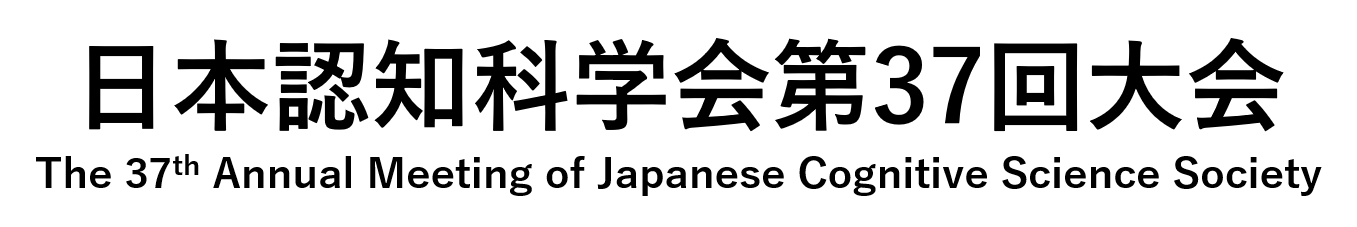研究分野別一覧
学習
-
OS07-4公募発表触発と社会的比較の理論に基づき,他者の小説作品を推敲することが読解する場合と比べて創造的な創作を促進するかを,心理実験によって検討した.48人の大学生・大学院生の実験参加者が4条件のもとで掌編小説を創作し、大学生・大学院生6名が創造性を評定した.分析の結果,他者作品を推敲することで,読解する場合と比べて創造が促進されることが明らかになった.
-
OS07-5公募発表芸術に関する知識や経験は作品鑑賞行為に影響することが知られている。熟達者が鑑賞時に注意を向ける点を特定した上で、初心者に対して同様の点に注意を向けるように支援することで、有効な鑑賞の支援となる可能性がある。著者らの実験結果(N = 103)では、専門家の提唱する形で作品創作プロセスの認識に注意を向けた参加者は作品への感嘆等が促進される結果となった。本発表では実験の紹介と共に、鑑賞支援に向けてどのような基礎研究が可能か考察する。
-
O1-2各種新型モビリティの提案を背景に,人と小型モビリティが混在する空間のデザインが問題となっている.本研究は歩車混在空間で生じるリスク,その低減行動の分析から,歩車間相互作用に影響を与える諸要因を検討するため,空港ならびに博物館でのモビリティと周辺歩行者の相互作用を観察した.その結果,運転ルール遵守もしくはコミュニケーションによるリスク低減行動が観察された.各問題点から歩車共存空間のデザインについて論じた.
-
O1-4本研究では,楽器演奏教示場面における,教示に対する理解の提示(デモンストレーション)としての学習者による演奏を指導者が「止める」実践を記述する.その実践には,演奏を「単に止める」場合と「中断する」場合の2つのやり方が見いだされた.それぞれが教師対生徒の教室内相互行為に特徴的なIRE連鎖と同じ構造を持つ行為連鎖に埋め込まれ構造化されることで,学習者の演奏を評価することも実質的に達成していることが明らかになった.
-
O2-2本研究の目的は,知識構築コミュニティの構成員が,自らの集団的認知責任を意図的に発揮させることを支援する方法を提案することである.この目的のため,電子掲示板を用いて活動する知識構築コミュニティにおいて,各構成員の集団的認知責任の指標をリアルタイムに可視化するためのシステムを社会ネットワーク分析を利用して開発し,学習環境デザインを支援するコミュニティにて実践した.その結果,コミュニティ構成員の相互貢献に資する活動が活発になる傾向が示された.
-
O3-2人工エージェントが多様な環境を学習するためには,内発的動機に基づく報酬が必要である.これまでに,エージェントの内発的動機づけの研究が行われてきたが,統合的なアーキテクチャの中で検討するものはなかった.本研究では,ACT-Rを用いて内発的動機づけの認知モデルの構築を目指す.モデルは環境中のパターンの発見を知的好奇心の源泉とみなす.それによって,モデルは複数の異なる広さの環境を学習することができた.
-
O4-4本稿では,「知識構成型ジグソー法」による理科の授業で同じ班に属した3名のプレポストテストと発話記録を「機能機構階層図」を用いて分析し,問題解決のヒントとなる知識を事前に渡すことが,生徒の理解に及ぼす影響について検討した.分析の結果,ヒント知識の提によって生徒の理解は授業の目標に向けて一定程度「収斂」するものの,各自の理解の固有性が失われるわけではなく、授業の過程では「建設的相互作用」が同時進行していることを確認した。
-
P-10Continuous Flash Suppressionを用いた閾下学習が作業手順の記憶効率と記憶定着に及ぼす影響を検討した.具体的には,複雑な系列からなる作業を分割し,1つの手順ごとに閾下呈示することで,①次の正しい作業手順を促すことが可能か,②作業手順全体の記憶定着を促進可能か,を検証した.実験の結果,1つの手順ごとに閾下呈示することで,①次の正しい作業手順を促すことが可能なこと,②作業手続きを記憶できる量が増加することが分かった.
-
P-11言語獲得初期において,animacyの高い参与者に焦点をあて事態を把握・描写する日英語母語幼児は,成長に伴い,前者はempathyの高い参与者に,後者はaction chainの開始点に焦点をあて,それらを主語として描くという違いを見せるようになる.本研究では,この違いが既に3歳児で現れること,更にempathyの高い参与者を主語とする際に重要な受身表現についても日本語母語幼児は3歳児の時点で一定の使用を見せることが明らかになった.
-
P-13Suzuki(2018)は,投資ゲーム(顔写真に示された人物を信頼して投資を行うかどうかを判断する課題)を繰り返し行う中で,高齢者は若年成人と異なり,信頼性判断の成績が向上しないことを示した.こうした高齢者の判断特性が真であるならば,それをいかに支援するかを検討する必要があり,本研究では若年成人との相互作用,例えば子や各種窓口担当者との相談が高齢者の意思決定過程に対して影響を与えうるか否かを検討するために,実験的検討を行った.
-
P-21知的障害児4名の学級において,担任2人と第一筆者がものづくり教材を使った協調的な授業を行った.その授業分析と担任インタビューの分析から,知的障害を伴う自閉症児1名の理解過程を明らかにし,活用性のある学びが起こる要因を検討した.その結果,課題遂行とモニタリングが交代して起こる授業デザイン,ルーティーン化と局所的正誤判断がつきにくい工程を含んだ学習活動,新しい学びへの期待,が要因として考察された.
-
P-22適応的なフィードバックを行う場合に,学習者の状態を検知する必要があるため,協同プロセスを推定できる表情モデルを作ることが重要である.本研究の目的は,学習プロセスごとに関連する表情を検討することである.分析方法として,学習プロセスごとにおける各表情の出現頻度を算出した.結果として,学習プロセスごとに異なる特徴的な表情が生じることが明らかになった.今後の課題として,より詳細に分析し,学習者の表情からICAPを定量的に捉える検討を行う
-
P-23本研究の目的は,プログラミング学習におけるあきらめやすい場面状況に対してどのような回避行動がとられるのかを整理することである. 調査の結果から因子分析を行い,あきらめることを回避する行動を5つの因子に分けることができ,その中にわりきり行動のような行動がとられる「わりきり的行動」因子が含まれていた. また,各因子に着目してあきらめの場面を分類した.その結果,原因の具体性によって効果的であると考えられている行動が異なることが示された.
-
P-24日本語の会話で頻繁に使われる「のだ」は、当該の命題を既定とみなす場合に用いられる談話標識である。これは、学習者にとっては習得が難しいと言われている。本研究は、事象関連電位の指標を用い、「のだ」の使用条件と非使用条件に応じて、「のだ」の有無に対する神経活動が母語話者と学習者とでどのように異なるかを比較した。両群で異なる成分が見出され、学習者による「のだ」過剰使用の傾向が非使用条件に対する理解に乏しいことに起因している可能性を示唆した。
-
P-27本研究では食品安全に関する知識について,食品と添加物,一般的知識と安全性に関する知識に分類し,尺度を作成した.この尺度を用いて高校生とそれより年齢が高い世代の知識量を測定し,両者を比較することで獲得する知識の違いを検討した.その結果,添加物に関する知識が食品に関する知識よりも獲得される知識が少ないことが明らかになった.本研究はその原因を探るための調査研究である.
-
P-29大学生活における留学,ゼミ,インターンシップ,ボランティアなどの活動は,学習ならびに日常生活における行動変容をもたらすと予想できるが,これらについての調査は発展段階にあり,認知科学的な観点からの検証が必要である(森下・有賀・原田・阪井・富田,2018).本稿では,多重知能理論にもとづく多重知能分析シートならびにTIPI-J(小塩・阿部・カトローニ,2012)を使用したアンケート調査およびそれらの相関分析の結果について報告する.
-
P-32本研究は、教育活動において生徒がどのように聞き手行動を用いてその場の相互行為を構築しているかを明らかにすることを目的とし、楽器レッスンにおける生徒の「はい」と「うん」の使い分けを分析する。楽器レッスンの録画データから「はい」と「うん」の事例を収集して分析した結果、「はい」はどのような演奏が望ましいかを述べる発話に対して反応する際に用いられるのに対し、「うん」は、楽曲についての説明に対する反応として用いられていることが明らかになった。
-
P-41新型コロナウイルスの影響で,各教育機関は遠隔授業の実施を求められるようになった.遠隔授業は一般に,LMSによる講義資料・課題の配布・回収や講義の動画配信にもとづく「オンデマンド授業」と,Zoomなどを使用した「リアルタイム授業」に分けられるが,授業の規模や内容によって向き不向きもあると考えられる.そこで,各授業形態のメリット・デメリットを検討するため,2020年前期の授業で,遠隔授業についてのアンケート調査を実施することとした.
-
P-42COVID-19感染拡大のためオンライン・オンデマンド授業で対面授業を代替する動きが盛んであるが、教員と学生・学生同士の対面でのインタラクションと言語的・非言語的コミュニケーションが欠落した場における教育・学習の難しさは教員・学生が実感しているところであろう。オンラインで教員学生間・学生同士間のインタラクションを可能な限り実現する努力をどのように進めるか、課題内容によって全人的な交流を促進するかの方策について多様な観点から検討する。
-
P-43本研究はスラックラインのコツについて,初級者と上級者を比較し明らかにすることを目的とする.スラックラインとは,ベルト状の綱の上で全身を協調させてバランスをとるスポーツであり,近年,バランス・トレーニングとしても注目されている.そのコツとして,両手の協調性に着目し,両群を比較した結果,上級者の方が片脚立ちをしている最中の両手が協調していることが示された.今後,熟達のコツや知覚・認知との関係を調べることで,リハビリなどへの応用に繋げたい.
-
P-452020年度から小学校でのプログラミング教育の必修化を背景に,本研究では,算数に対する小学校の児童の意識がプログラミングの特徴に影響を与えるか調査した.公立小学校5年生145名にプログラミングを用いた正多角形の性質を学ぶ授業を,図形描画で色が変化するカラフル条件と単色条件に分けて実施した.アンケートの分析及び発話分析の結果から,カラフル条件は,単色条件より児童が工夫してプログラミングに取り組む主体的な問題解決を促す可能性が示された.
-
P-55今日の博物館教育においては,博物館内での体験から得られた学びが来館者の日常へと活かされることは重要な目的の一つである.本研究では,特に美術館教育を念頭に置き,日常的に身の回りにある対象への知覚や理解の変化を促す美術鑑賞のワークショップ実践と,その効果検証を行う.特に効果については,事前・事後調査により測定することに加え,ワークショップ中のプロセスに関しても多様な側面から検討を行う.
-
P-61本研究では,師匠と習い手が向かい合い,互いの演奏が観察可能な状況で同時演奏を基調に進められる三味線の稽古を観察し,師匠によるマルチモーダルな指導に焦点を当てた分析を行った.その結果,師匠は自分の演奏から手が離せない状況の中で,指遣いの特徴や定型的な旋律を参照しつつ端的な発話で指示を出し,頭部と視線の動きも活用しながら習い手の演奏を巧みに指導していることがわかった.また,こうした対面・同期形式で行う稽古の意義についても再考した.
-
P-65人が目的地までの経路をナビゲートする時, 近道を 発見し目的地に短距離で到着する人と,近道を発見せ ず回り道で到達してしまう人に分かれる. 今回の研究 では, 其々のパターンに見られる視線を計測した。こ の計測データから, 近道を発見する人がナビゲーショ ン中に見せる視線の動きと, 遠回りをする人がナビゲ ーション中に見せる視線の動きの違いを分析する.
-
P-69本稿は,学校地域間連携活動における境界の重層的な横断によるボランティア間の相互作用に着目する.分析の結果,ボランティアは,活動への十全的な参加度合いを境界として実践的知識をやり取りし,外部からの異質な視点を用いて,他者からの知識を解釈,調整して自らの実践へと適用していた.また,協働的な実践を通じたボランティア間の関係性構築により,企業生活などの外部活動に関する視点交流が行われ,世代性という新たな境界の生成という境界の動態性が示された.
-
P-72本研究では,人が記号的なコミュニケーションにおいて字義通りの意味と言外の意味を共有・学習するメカニズムを,メッセージ付きコーディネーションゲームを用いた計算機シミュレーションにより調査した.結果,我々が構築した計算モデルが,他者の言外の意味を同義語・同音異義語の数から推定する方法を持つ場合に,人どうしの実験データをより良く再現することを確認した.本論ではこの結果に基づき,人が持つ記号への意味づけとその共有のメカニズムを議論する.
-
P-79読みにくい文字は記憶成績を高めるが,その効果(非流暢性効果)は頑健ではない。その要因として,非流暢性の程度やワーキングメモリ容量(WMC)が考えられる。そこで本研究は,文字の流暢性のレベル(4段階)とWMCが単語記憶に与える影響を調べた。実験の結果,非流暢性効果は確認できなかった。この結果は,一つの刺激リストの中に特徴的(非流暢)/非特徴的な文字を混ぜて呈示した場合に非流暢性効果が発生しやすいこと(対比効果仮説)を示唆する。
-
P-80本研究では,小学校の算数の授業における,アクティブ・ラーニングとして導入されたグループ活動での児童の対話を対象とした.学校文脈での学びを日常経験文脈に照らしながら児童がどのように思考を広げ,深めていくのかという対話的展開過程を明らかにすることを目的とし,実証的に検討した.それらの結果から,学校と日常の非対称性が,対話という相互行為の文脈で,いかにして児童に捉えられ,教授・学習が実現されているのかが明らかになった.
-
P-86本研究では、非対格動詞(自他交替有り)の習得について、他動詞文、自動詞文、過剰受動文の容認・否認の観点から学習者の形成する中間言語規則を類型化して分析した。その結果、主に5つの類型が見られた。英語熟達度が上がっても変化せず、化石化の可能性のある類型も見られた。中間言語規則は、目標言語規則に向かってまっすぐに再構築されるとは限らないことも示唆された。長期観察等による研究が課題となった。
-
P-87本研究は,呈示する他者の意見に含まれる意見の多様性に着目し,多様性の違いが自身の意見変化に与える影響の調査を目的とする.そこで,「教育における新しいメディアの利用」に関する意見を求める課題を設定し,多様性の異なる他者の意見を呈示する前後において,自身の意見変化に与える影響を検証するための実験を行った.結果として,多様性の高い他者の意見の呈示が意見変化における文章内容の質の向上を促す効果が見られた.
-
P-90本研究では,身体技能習得における「気づき」を呼び起こす手段として「付加的情報フィードバック」の手法に着目し,これをピアノ演奏におけるペダリング練習に適用した.演奏中のペダル踏み込み量をオンラインまたはオフラインで学習者に提示することで,学習者はペダリング時の身体感覚と響きの変化との関係性を効果的に習得できることが期待される.本稿では本システムの効果について著者自身の「気づき」に関する経験に基づき議論する.
-
P-91本稿では、VR空間内に多面体を提示しユーザがそれらを仮想的に操作するようなシステムを開発し、実空間上にて観察された身体的な関与がVR空間でも観察されるかどうかを検討する。今回のVRシステム実装では、両手の十本の指で面を押さえるという動作を仮想化することが十分にできなかったため、満足できる結果は観察されなかったが、改良すべきポイントや認知科学的な観点について考察を行うことができたので、そのことを報告する。
-
P-92南極観測隊員延74人を対象に,自然環境内のリスク特定・評価の特徴と経験による変化把握のため,課題1(リスク特定課題)と課題2(リスク評価課題)が実施された.南極観測経験によるリスク評価の違いは限定的ながら,経験無群>経験有群の有意差が得られたものが見られた.また,経験無群での南極滞在前後のリスク評価では,事後のリスク評価の低下が広範に見られた.結果から,経験によりリスク発現場所について弁別的なリスク知覚がなされることが示唆された.
-
P-98新型モビリティの登場により,歩車混在空間における人―移動体間のリスク共有の重要性が増している.本研究ではライトレールを取り上げ,横断歩道における歩行者との相互作用とコミュニケーションの特性を検討するための行動観察を行った.その結果,運転者が歩行者の行動に応じてリスク回避行動を取っているが,歩行者にはそれが伝わっていない様子が観察され,歩車共存空間におけるコミュニケーション支援の重要性が示された.
-
P-101人は,現象を説明可能な解釈が無数に存在するときでも一つあるいは少数の解釈を選ぶ傾向にある.本研究では,こうした認知処理の傾向を「思い込み」と呼び,数理的な定式化を目指し研究を進めた.具体的には,トイモデルとして画像回転課題を提案し,事前制約と学習効率の関係について数値実験による分析を行った.
-
P-111教室での教科書を使った学習になじめない児童・生徒に対して,活動をベースにした学び(ABL:Activity Based Learning)を実施した。参加児童・生徒が在住している地域の大通りの長さを限られた道具で測定するミッションを提示し,参加者それぞれが作戦を立て測定を行わせた。活動を通して,共通の場から各自の学習の習熟度や興味関心に沿った個別化された学びを達成し,さらに,発展的達成型ゴールを設定して次の学びへ向かう姿勢が観察された。
-
P-112本研究は,子供の逆上がりスキルの獲得過程に対して,運動アナロゴンの獲得も目指しスイング遊びを実践しつつ,身体知のメタ認知を実践した.分析はパフォーマンス分析と,発話と動作の見えるシステムを活用した.本研究の分析の結果から対象とした被験者は逆上がりができるようにはなっていないものの,スキル獲得の過程として足を蹴り上げている様子がインタビューと動作解析の結果から示唆された.
-
P-120様々な社会的場面において,人同士のインタラクションでは行動の探り合いが発生する.本研究では,インタラクションの継続と終了に至るプロセスを検討する.そのために,インタラクション課題として多義的な目標構造を有する鬼ごっこ迷路ゲームを用いて,人同士の行動変化の分析を行った.その結果,役割によって行動パターンの変化が異なり,行動の収束がインタラクションの終了につながったことが示唆された.
-
P-123本研究では,協力ゲームhanabiを題材として,飽きと学習の関係性を身体動作や内発的動機の観点から探る.加えて,ゲームスコアやゲーム時間などの時系列データも扱う.それらの分析過程において,身体動作から動きの周期性を抽出し,それを新たな指標として提案する.この指標を用いて,動機づけがうまくいく集団とは動作間隔の周期性が類似している集団であると結論付けた.
-
P-126主観的な感覚が身体運動に与える影響を明らかにするため「まるで〇〇であるかのように感じながら身体を動かす」という教示における身体運動をモーションキャプチャ及び表面筋電図により計測した.右上肢を用いた鉛直方向の到達課題において,「手の動きが直線的になるよう上に動かす」「上から吊られているように感じながら動かす」という二つの指示における運動を計測すると,いずれも直線的な手先軌道が実現された一方で,条件間では関節や筋の使い方に違いが現れた.
-
P-127Web上でのユーザの行動は多様化している.この多様化している行動は明確な目的を持たないブラウジングと明確な目的を持ったサーチングに分けることができる.本研究では,強化学習における探索と搾取がブラウジングとサーチングに対応すると考え,ACT-Rを用いてそれらを再現する記憶モデルを構築した.この記憶モデルをWeb環境に統合することにより,ユーザの行動に応じた支援を行うための枠組みを提案する.
-
P-128対話型授業のグループ活動における個々人の話量と理解度は相関するのかを明らかにするために,「知識構成型ジグソー法」7授業61グループ172名の発話量と学習成果の相関関係を調べた.授業によって学習成果の到達度は多様だったが,どの授業でも多く話す生徒が理解を深めるという単純な正の相関があるとは言えなかった.相関の低さは,主に話量は少なくとも理解を深めている生徒の存在ゆえだと考えられた.
-
P-138本研究は,フランスにてPuisais, J. が1975年に始めた味覚教育の理論を援用し,味覚教育の実践を行ったものである。イメージマップに着目して効果の検討を行った結果,「おいしさ」という刺激語から連想される語の数およびリンク階層数のいずれについても活動後に増加していることが示された。また活動後の連想語の内容から,「あじ」は味覚を含めた五感のいずれからも生じ得るという学習が味覚教育によって促進されている可能性が示唆された。
-
P-145本研究では,参照する試行履歴の情報源に関する認識が学習に及ぼす影響を検討した.大学生37名が実験に参加し,水槽課題に2回取り組んだ.2回目の取り組み時に,1回目の参加者自身の試行履歴を「自己のもの」として与えられる自己履歴条件と,「他者のもの」と偽って与えられる偽他者履歴条件の2条件が設定され,学習成績と試行履歴参照時に考えていたことが比較された.学習成績に条件間で差は認められなかったが,試行履歴参照時の着眼点が異なることが示された.
-
P-152本研究の目的は,学習者の状態に基づかないプロンプトの提示によってInteractive,Constructive,Activeが促進されるのか実験的に検討することである.そこで,それぞれの会話活動に関するコーディング基準に基づいてプロンプトを作成し,ランダムにプロンプトを提示した.その結果,プロンプトを提示された学習者は提示されなかった学習者よりもInteractive,Constructiveに関する発話をより多く行うことが分かった.
-
P-153ヒトは不確実状況下ではどのように意思決定を行い,その意思決定を形作る過程である学習はどのように行われるのだろうか.本研究では,不確実状況下における意思決定モデルであるプロスペクト理論の確率加重関数に焦点を当て,確率加重関数の過大評価,過小評価は,良い結果と悪い結果に対する非対称な学習から起きるリスク態度の反射効果により形成される可能性があることを示す.
-
P-155視覚情景の類似度判断において要素自体と要素の並びのどちらが手がかりになりやすいかを1-gram類似度と3-gram類似度を調整した階段法で調べた.刺要素と要素の並びの頻度に注目するために作成した無意味刺激を用いた.本研究は一度しか見ていない情景の記憶は,情景同士がよく似ているとき,時間的に近接している情景の要素の並びが近接していないときと比べて類似度判断の手がかりとなりやすいことを示した.