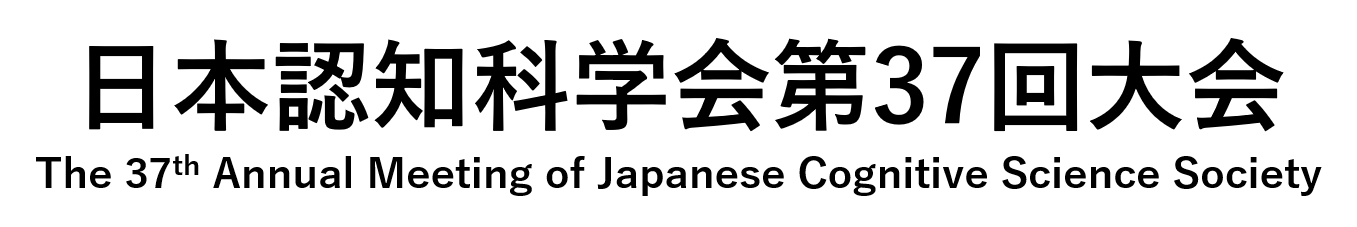研究分野別一覧
言語
-
O1-4本研究では,楽器演奏教示場面における,教示に対する理解の提示(デモンストレーション)としての学習者による演奏を指導者が「止める」実践を記述する.その実践には,演奏を「単に止める」場合と「中断する」場合の2つのやり方が見いだされた.それぞれが教師対生徒の教室内相互行為に特徴的なIRE連鎖と同じ構造を持つ行為連鎖に埋め込まれ構造化されることで,学習者の演奏を評価することも実質的に達成していることが明らかになった.
-
O3-3本論文は,文理解の認知モデル化に経済メカニズムデザインを適用することを試みた.文中の単語をエージェントのメッセージとみなし,文の意味は残余のゲームフォームに代入されて計算されると仮定された.具体的に総記のガや対比のハの解釈の切替え戦略に着目し,WordNetを用いて述部の静と動の示唆的特徴語の分布を調べ,ブロッキングシステムとして定式化した.また戦略的操作可能性から総記や対比の発生の具体的なモデルを提案した.
-
O4-1アンカリング効果とは, 事前提示された数値が後続の数量判断に影響を与える現象である. これまでの研究では, アンカリング効果が数値と意味のどちらのプライミングによって発生するのかを議論してきたが, 数値, あるいは意味プライミングのみでアンカリング効果が実際に生じるのかどうかを検討していない. 本研究の結果は, アンカリング効果の発生には数値と意味プライミングを誘発する刺激の2種類を同時に提示する必要があることを明らかにした.
-
P-3英語の複合語処理には第2形態素の意味的透明性の影響が大きいとされているが大半が第2形態素が主辞のため主辞と意味的透明性の影響が不可分である。日本語には第1形態素が主辞の複合語もあり影響を分離検討できるはずだが,主辞の形態素の意味的透明性が低い複合語が存在するか疑問だった。本研究では主辞の位置の異なる複合語の各形態素の意味的透明性を調査し,主辞の形態素の意味的透明性が低い複合語の存在を確認し,分類検討のための刺激語選定の予備データを得た。
-
P-4会話において特定の対象を参照する際,発話の途中にポーズを入れ,会話相手の対象への知識について反応を伺う方略が使われることがある。Clarkら(1986)は,こうした方略によって,会話における共同のエフォートを最小化すると述べている。しかし,実際の会話データを用いた検証は行なわれていない。そこで,本研究では,日本語地図課題対話コーパスを用いて,分割提示の実際について数量的な調査を行いその効果について検討を行った。
-
P-5本研究では主題に付与された特徴の数が名詞比喩表現の産出に与える影響を検討する。2つの実験で、参加者は呈示される文の言い換え課題に取り組んだ。呈示される文の主題に付与される特徴の数が操作された。結果、2つの実験のどちらでも、主題に付与される特徴の数が増えるにつれて名詞比喩表現の回答割合が増えた。私たちの結果は主題に付与される特徴の数が比喩表現の使用に影響することを示唆した。比喩の産出と選好に関する先行研究に基づいて結果を議論した。
-
P-8本研究では、物語文の萌芽期の発達の特徴を内容面に着目して考察した。日本語を母語とする3歳前半と後半の幼児の物語文をKH Coder 3を使用したテキストマイニングの手法により、頻出語、共起ネットワークを検出して分析した。その結果、絵本の各場面における主人公や登場動物の行動の絵描写的な内容から、行動の背景となる場面についても空間的、時間的な視点から言及し、主人公の心情にも触れる発達過程が明らかになった。
-
P-11言語獲得初期において,animacyの高い参与者に焦点をあて事態を把握・描写する日英語母語幼児は,成長に伴い,前者はempathyの高い参与者に,後者はaction chainの開始点に焦点をあて,それらを主語として描くという違いを見せるようになる.本研究では,この違いが既に3歳児で現れること,更にempathyの高い参与者を主語とする際に重要な受身表現についても日本語母語幼児は3歳児の時点で一定の使用を見せることが明らかになった.
-
P-19本研究では,英語の結果構文の獲得について,子どもの発話データベースCHILDESに基づき調査を行い,その結果を踏まえ,形容詞を伴う結果構文(RC-Adj)と前置詞句を伴う結果構文(RC-PP)との関係について明らかにする.言語獲得の初期段階では,RC-Adjに比べるとRC-PPの発話頻度が高い.その理由についても,子どもの発達過程を考慮に入れつつ,構文文法論の観点から両者の構文特性が関係していることを示す.
-
P-24日本語の会話で頻繁に使われる「のだ」は、当該の命題を既定とみなす場合に用いられる談話標識である。これは、学習者にとっては習得が難しいと言われている。本研究は、事象関連電位の指標を用い、「のだ」の使用条件と非使用条件に応じて、「のだ」の有無に対する神経活動が母語話者と学習者とでどのように異なるかを比較した。両群で異なる成分が見出され、学習者による「のだ」過剰使用の傾向が非使用条件に対する理解に乏しいことに起因している可能性を示唆した。
-
P-25身体化認知の枠組みに基づいて,意味記憶が運動と処理資源を共有するという考えが提案されてきた.本研究の目的は,手で操作可能な物体の操作的知識に対して運動シミュレーションが与える影響とそのメカニズムを明らかにすることである.本研究では単語刺激を用い,手で操作できる物体の意味処理を行う際に身体拘束がどのような干渉効果を及ぼすのかをNIRS(近赤外分光法)を用いて計測した.
-
P-26本研究では,仮想現実における「視点の変換」によって人間の思考や行動が変化する可能性があることに着目した.実験参加者には,「仮想現実内で視点が高くなる」体験をさせ,その際,言語教示として「巨大化」と「浮遊」の二通りの捉え方を与えた.その結果,この2つの言語教示によって行動が異なる可能性があることが示唆された.またこの言語教示の違いによる行動の変化には,実験参加者の想像力の影響があることも分かった.
-
P-29大学生活における留学,ゼミ,インターンシップ,ボランティアなどの活動は,学習ならびに日常生活における行動変容をもたらすと予想できるが,これらについての調査は発展段階にあり,認知科学的な観点からの検証が必要である(森下・有賀・原田・阪井・富田,2018).本稿では,多重知能理論にもとづく多重知能分析シートならびにTIPI-J(小塩・阿部・カトローニ,2012)を使用したアンケート調査およびそれらの相関分析の結果について報告する.
-
P-30概要 大学生に,題材が 誤信念理解 の民 話を画面で読み聞かせ , 2肢 又は 4肢選択の誤信念理解検査成績 ,類推 及び作業記憶 と 絵本の内容理解 を関連付けた 実験 の一環 である。聞き手の作業記憶での 誤信念内容 の 選択 ,聞き手自身の視点又は 真実 の 抑制 と 類推に よる理解促進 を 述べた 。
-
P-32本研究は、教育活動において生徒がどのように聞き手行動を用いてその場の相互行為を構築しているかを明らかにすることを目的とし、楽器レッスンにおける生徒の「はい」と「うん」の使い分けを分析する。楽器レッスンの録画データから「はい」と「うん」の事例を収集して分析した結果、「はい」はどのような演奏が望ましいかを述べる発話に対して反応する際に用いられるのに対し、「うん」は、楽曲についての説明に対する反応として用いられていることが明らかになった。
-
P-35本研究では,記号的なコミュニケーションの成否が,人間の調和的な性格特徴によって影響されるかどうかを調査した.具体的には,既存の心理尺度による調和性指標に基づき実験群を構成し,二者間で人工的な言語を作る課題の成績との関係性を調べた.結果,両者には有意な関係性は確認されなかった.これは,ことばによるコミュニケーションの成否が,単純に性格特徴によって決定されるものではないことを示していると考えられる.
-
P-44左上側頭回における脳出血後に他の言語障害の併発が少なく,外国語様アクセント症候群 (FAS) の症状を呈した対象者のアクセント錯誤を例に,日本語のアクセント情報の符号化過程について議論を行う.特に対象とするのは,いわゆる平板型に属する語におけるアクセントの音韻情報についてで,これは情報として空虚である可能性について論じる.
-
P-462つの概念の組合せによりユーモアが生起される「なぞかけ」を取りあげ,印象変化とユーモアの関連について検討した.本研究では,日本語評価極性辞書を用いることで単語印象を考慮したなぞかけ生成モデルを構築し,シミュレーション結果を用いた心理実験により,オチの提示による先行単語の印象変化と変化とユーモアの関連について明らかにした.その結果,先行単語そのものの印象とオチの提示による変化がユーモアに寄与している可能性が示唆された.
-
P-48学習課題時に中3の教科書ガイドを音読または黙読することで,また,テスト課題時にリーディングスキルテストを音読か黙読することで,読解力が変わるか調べた.103名が6群に分けられた.学習課題は,音読群,黙読群,学習なし群に,リーディングスキルのテスト課題は,音読群と黙読群に分けられた.教科書ガイドの事前の黙読または音読によって,参加者は読解力を向上させた.また,リーディングスキルテストを音読した場合よりも黙読した方が,読解力が高くなった.
-
P-54本研究では,日本語の会話においてしばしば見られる,参与者が日本語標語話者であるにもかかわらず,標準語以外のなんらかの方言,典型的には関西方言に属する語彙や表現を用いて発話するという現象について分析を行う.字義的に提示されている行為とはなる理解を促すためのメタメッセージを発話にもたせることを可能にしており,そのメタメッセージが場合によっては冗談であることの理解や,譴責どの行為の持つリスクへの対処になっていることが明らかになった.
-
P-61本研究では,師匠と習い手が向かい合い,互いの演奏が観察可能な状況で同時演奏を基調に進められる三味線の稽古を観察し,師匠によるマルチモーダルな指導に焦点を当てた分析を行った.その結果,師匠は自分の演奏から手が離せない状況の中で,指遣いの特徴や定型的な旋律を参照しつつ端的な発話で指示を出し,頭部と視線の動きも活用しながら習い手の演奏を巧みに指導していることがわかった.また,こうした対面・同期形式で行う稽古の意義についても再考した.
-
P-63要素の結合と言語形式がどのように比喩性の把握に影響を及ぼしているのか,比喩指標要素と要素の結合を含む用例を用い,用例全体(直喩)と要素の結合(隠喩)のそれぞれについて,比喩性の評定を付与した.用例全体と要素の結合の評定差を調査した結果,結合そのものの影響というよりも広く文脈が比喩性の把握に関わっている可能性が見られた.また,結合の種類により,比喩性の把握における指標の有用性が異なっていた.
-
P-64本発表では,ストーリーの創造性の計算原理を探求する研究の一環として,FauconnierとTurnerによるConceptual Blending理論に示唆を得た,事象融合の計算モデルを示す.このモデルは,二つの入力事象を構造的に組み合わせて,一つの融合事象を生成する.発表及び予稿では,その仕組みを詳しく説明する.また,本モデルと人による事象融合を比較する実験を通して,本モデルの創造性の程度や性質に関する分析的な検証も行う.
-
P-67本研究では、条件文の形式を持ちながら、前件と後件の間に依存関係がないという特徴を持つBiscuit Conditional、(後件の明示されない前提が強化された)unconditional presuppositionを投射するunconditional sentence 、および、誤謬推論を比較し、その異同を糸口に、誤謬推論が生じるメカニズムの解明を目指す。
-
P-72本研究では,人が記号的なコミュニケーションにおいて字義通りの意味と言外の意味を共有・学習するメカニズムを,メッセージ付きコーディネーションゲームを用いた計算機シミュレーションにより調査した.結果,我々が構築した計算モデルが,他者の言外の意味を同義語・同音異義語の数から推定する方法を持つ場合に,人どうしの実験データをより良く再現することを確認した.本論ではこの結果に基づき,人が持つ記号への意味づけとその共有のメカニズムを議論する.
-
P-74物語読解では,単語や文といった局所的意味の理解と,物語全体の意図といった大局的意図の理解が相互依存的になされる.この物語における局所/大局的理解の関係性を調べるため,本研究では,布山・日高(2019)で提案された2つの課題を用い,オンラインでの認知心理実験を行なった.その結果,両課題の成績(正答や参加者間相関)に正の相関傾向が示唆され,局所/大局的理解の関係が示唆された.
-
P-84本研究では, 中国語を母語とする上級日本語学習者のデフォルトのアクセント型が, 日本語母語話者の発話とどのように異なるのかを, 無意味語の発話実験を通じて調査した. 日本語母語話者は3モーラ語で頭高, 4モーラ語で平板型の適用が多く見られた.中国語母語話者は, 4, 3モーラ語両方で平板型アクセントを使用した. 実験の結果, 中国語人上級学習者と日本語母語話者の文法との間には違いがあることが分かった.
-
P-86本研究では、非対格動詞(自他交替有り)の習得について、他動詞文、自動詞文、過剰受動文の容認・否認の観点から学習者の形成する中間言語規則を類型化して分析した。その結果、主に5つの類型が見られた。英語熟達度が上がっても変化せず、化石化の可能性のある類型も見られた。中間言語規則は、目標言語規則に向かってまっすぐに再構築されるとは限らないことも示唆された。長期観察等による研究が課題となった。
-
P-93ユーモア理解において不調和の感知段階と解消段階という過程が関与し,ユーモアを生じる要の解消段階において扁桃体が重要な役割を果たすことが示唆されている.扁桃体は,一見すると明示的ではない隠れた敵意や社会的な脅威などの関連性感知に関与する神経基盤と考えられている.また,保護されているという認識を伴った遊び状態の重要性が指摘されていることも合わせて考えると,ユーモア理解は扁桃体のこのような役割を利用した一種の遊びと考えられる.
-
P-94L2学習がL1の音韻体系を再構築することが知られている.本論文は,日中バイリンガル標準中国語話者を対象に発話実験を行い,L2である日本語の習得が,L1の中国語の母音体系に影響を与えるのかを調査した.音声の音響分析を行い,フォルマント周波数(F1, F2)を基に母音空間図を作成し,話者群間の比較を行った結果,高母音(/i/,/u/)の舌の高低に違い見られ,後舌高母音(/u/)の円唇度は,L2を学習した場合,強まることがわかった.
-
P-116日常生活で間断なく行われる会話は,二重課題性を持っているために,高齢者はその実施に困難を示し,高齢者と会話する若年成人の負担感の原因となっているのではないか。もしそうであれば,二重課題訓練を行うことで,高齢者の会話困難とそれに伴う若年成人の負担感を減少させ,ひいては世代間コミュニケーションを推進できる可能性がある。その可能性を検討するため,会話の二重課題性を純粋に反映するものとして追唱課題を用いて,実験的検討を行った。
-
P-118人型ロボットPepperを一般家庭に貸与し,1ヶ月間一緒に暮らしてもらった.どのような場面で人がロボットを単なる機械ではなく心を持った相手として接するのか調べた結果,挨拶場面,Pepperに不具合が生じた場面,人がPepperを模倣する場面,褒める場面,叱る場面,笑いが生じた場面を観察することができた.これらが親密性を高める要素となり,その組み合わせや,重層的な相互行為が関係性構築に関わっていることが示唆される.
-
P-129人が音声を認識する際には,音韻の単位に関するいくつかの処理が必要になる.それらの処理の一部は音韻意識と呼ばれる能力によって制御される.本研究の目的は,認知アーキテクチャACT-Rの知識検索の仕組みに対応づけて,音韻意識をモデル化することである.とくに音韻意識形成過程に見られる誤りとその要因に着目する.音韻意識形成がかな文字の習得と関連することから,活性化拡散を用いた視覚的補助の効果を検討する.
-
P-130本研究では、語用論的推論における非言語情報の影響を検討した、実験では、実験者があるイラストに注目している、と言及した。このとき3つのイラストが表示されたモニターに指さしを行うか行わないか、さらに実験者の視線方向を参加者に向けるか、対象に向けるかを操作した。結果、実験者が指さしをしないで指示した方が、合理的解釈に基づいた選択や顕著性に基づいた選択を行っていた。合理的解釈に基づく人間の推論は、非言語情報の影響を受けるということが示唆された。
-
P-131本研究は遠隔会議を利用したリモート漫才が通常の対面漫才対話と異なり対話リズムにおいて修復されるべき「トラブル」が生じやすいため,それらを演者が相互に調整しリズムの修復を行っていく過程が観察可能である点に着目し両者の対話音声の分析に基づいてその修復プロセスの解明を目指したものである.分析の結果,対話リズムの修復に対して二種類の修復ストラテジーに基づく演者間の相互調整が寄与していることが明らかとなった
-
P-132笑顔や良い姿勢は嬉しさや誇らしさなどのポジティブな感情や上の空間情報を促し,しかめ面や悪い姿勢は悲しさや落胆などのネガティブな感情や下の空間情報を促すということが先行研究でわかっている.私達は日々の生活の中で様々な「解釈」を行なっているが,その解釈には自分自身の「表情」や「姿勢」はどのように影響しているのだろうか.本研究では,表情や姿勢が2通りの解釈が可能な多義文の理解に与える影響について選好判断課題を用いて検証する.
-
P-133先行研究では言語によって時間の言語表現が異なるだけではなく、時間の捉え方自体も異なると述べている。本研究では、時間を量概念を用いて表現する傾向が強い日本語話者を対象に、「線の長さ」または「量の多さ」のプライミングが速度が曖昧な時間事象の捉え方に与える影響を検証した。反応時間に有意な差は見られなかったが、正答率の結果から、線概念よりも量概念の活性化が、日本語母語話者の速度が曖昧な事象の解釈(時間の捉えやすさ)を容易にしたと考えられる。
-
P-137同じ言語を共有しない話者間における「言葉の壁」の要因の一つは,言語の恣意性にあると考えられる。そこで,音声と指示内容の結びつきは完全に恣意的ではないことを示すブーバ・キキ効果を利用することで,限定的な状況であれば,話し手の伝えたい内容を聞き手に伝えられるのではないかと考えた。オノマトペは,音声と指示内容の間の関係が強いと考えられており,ブーバ・キキ効果が起きやすいと予想されるため,本研究ではオノマトペの指示内容の伝わりやすさを検証する。
-
P-141Japanese speakers prefer non-agentive expressions when describing events that equally allow agentive (e.g., ‘I dropped the keys’) and non-agentive (e.g., ‘The keys dropped’) descriptions (Choi, 2009; Teramura, 1976). However, they are more likely to use agentive expressions when describing intentional events (Fausey, Long, & Boroditsky, 2009). This study examined how native Japanese speakers comprehend and construe the agents of unintentional and intentional events in sentences with unspecified agents of blamable acts. The results support that listeners flexibly adopt an agent’s or observer’s perspective given explicit grammatical pronouns (“I” or “the other”) in Japanese, and they consider another person to be the agent of negative events.
-
P-150日本語容認度評定データ (ARDJ) 構築の第一期と第二期の調査で刺激文に使われた466文の読み時間データを追加収集し,評定値データと対応づけた.そのデータの多変量解析と回帰分析の結果から,容認性判断とそれに要する時間は,刺激文を分割された部分への反応時間からは予測できない事が示唆された.ただし元になった反応時間データに代表性が保証されていないため,結果の一般性には自ずから限界がある.