
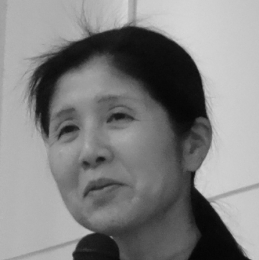
1.はじめに
原田悦子先生,この度は認知科学会フェローの受賞,誠におめでとうございます.筆者らは, 2001年の頃より,共同研究者,教え子として研究のご指導を頂きました.他にも多くの教え子の皆様がいらっしゃいますが,代表してこの紹介記事を執筆させて頂きます.
2.これまでの歩み
原田悦子氏は,筑波大学大学院心理学研究科博士課程にて単位取得後,日本アイビーエム㈱東京基礎研究所の認知工学研究チームに研究員として参加しました.大学院では,潜在記憶に関する記憶研究に従事し,実験心理学者としての基礎を築かれ,日本アイビーエムの東京基礎研究所で実験心理学をベースとする認知科学者としてのキャリアをスタートされました.その後, 1989年に法政大学社会学部専任講師として赴任され,学生と共に認知科学の研究を進めることになりました.法政大学では 1991年に助教授, 1998年に教授となりました. 2010年に筑波大学大学院人間総合科学研究科(心理学専攻)に異動して教授となり, 2024年 3月にご退職されました.ご退職されるまでの間, 1990年に教育学博士の学位を取得, 1995年から 1年半 McMaster大学心理学科客員研究員, 2007年には 1年間, Toronto大学心理学部の客員教授で在外研究をされました.
現在は,筑波大学名誉教授・客員教授として活動しつつ,株式会社イデアラボでリサーチディレクター(サイエンスコミュニケーション事業部)として認知科学の研究と「心理学の社会貢献」推進の支援をされています.
原田氏と筆者らが出会ったのは原田氏が法政大学に所属されている時であり,それ以来,ご指導いただきながら二十数年にわたり共同研究を行ってきました.本稿では,筆者らが知るかぎりではありますが,これまでの原田氏の研究活動について俯瞰的に紹介させていただきます.
原田氏の研究分野は多岐にわたりますが,主な分野として記憶や注意,加齢を対象とした認知心理学的研究,人 .人工物のインタラクションやユーザビリティのテーマを中心とした認知工学的研究が挙げられます.これまでの原田氏の研究の姿勢を象徴する言葉は,「生活の中での活動にこそ人間の認知の真実がある」だといえます.原田氏の研究者としての活動を通じて一貫して示してきたのは,人間の認知が日常生活での社会的・文化的文脈においてどのように現れるかを実験法を中心に様々な研究法を用いて丁寧に見つめようとする姿勢であり,その姿勢のもと,多くの学生,共同研究者らとともに認知科学の新たな地平を切り拓いてきました.とりわけ,この 10年は,市民を重要なステークホルダーと考え,彼らと共に,生活のなかでの人工物のユーザビリティを民主的に探究する「みんなの使いやすさラボ(みんラボ)」を筑波大学近隣(茨城県南地区)に在住の高齢者のみなさんと実践されています.みんラボの取り組みは,原田氏の研究の形の一つの到着点であると考えられ,その取り組みは国内外を通じて特異かつ独創的なものとして高く評価されています.ここではみんラボでの実践に至るまでの原田氏の研究活動を 3つの観点から紹介したいと思います.
3.認知心理学から認知科学へ
原田氏の研究は,筑波大学太田信夫先生の研究室での潜在記憶に関する記憶研究が出発点です.ただし,単語のプライミング効果そのものではなくプライミング効果という現象から,人間の認知の統合的処理の様相について新たな視点を提供しようとする研究を行われていました (原田 , 1987, 1996).筑波大学大学院の時代から,記憶という人間の認知のパーツに留まらず,人間の認知過程全体を理解することに興味を持たれていたようです.これは, 1983年に日本認知科学会が設立されたことからもわかるように当時の認知科学研究興隆の気運の中,学内外で開催された研究会等での様々な研究分野の研究者らと交流した経験が影響しているようです.筆者や学生たちとのゼミや研究会でも,そのような研究会で先輩方に鍛えられた,とよくおっしゃっていました.また,大学院での実験心理学のトレーニングは,原田氏の研究で実験統制を丁寧かつ徹底的に行うベースとなっていると感じています.
4.認知工学研究─使いやすさ研究
原田氏は,大学院の後,日本アイビーエム㈱の東京基礎研究所で,情報科学や工学の研究分野の研究者らの中で,本格的に認知科学者として認知工学の研究を始めました.研究所では,当時日常や仕事の環境の中で使い始められるようになってきた最新の情報機器であったパーソナルコンピュータを取り巻く課題について研究を進められました.特に,コンピュータや情報機器が私たちの生活を支える道具となるために解決しなければならなかったインタフェースの「使いやすさ」の課題や,情報機器を用いた人間の知的な活動に関する理解の必要性について多くの気づきを得られたようです.
東京基礎研究所で積み上げた情報機器をはじめとした人工物の使いやすさに関するリサーチクエスチョンは,次に赴任された法政大学社会学部で,学生と共に精力的な研究によって取り組まれることになります.それらの研究で行われた様々な実験は,原田氏が 1997年に上梓した『人の視点からみた人工物研究─対話における「使いやすさ」とは』 (原田, 1997)にまとめられています.この本では,原田氏がターゲットとした人工物について「人と人工物の最適な相互作用」の形を探るべく,認知心理学をベースとした巧みな実験統制による様々な「状況」で行った相互作用分析が報告されています.一連の研究の報告には,原田氏の研究の大きな魅力である大胆な仮説と仮説検証のための緻密な条件設定が組み込まれており,本書に対する書評 (堀, 1998)において「著者の一連の仕事の流れの中に,読者はぐいぐいと引き込まれていくことになる」と評されているように,認知科学における認知工学研究の面白さをアカデミアの研究者だけでなく,企業等の現場で認知工学に携わる多くの研究者らに伝えました.出版後,この書籍で興味を持たれた多くの企業の現場の研究者らと交流され,認知科学,認知工学の面白さを伝えながら活発に研究を進められていました.
5.認知的加齢研究と使いやすさ研究の融合
原田氏は,法政大学において認知工学の研究を進めると同時に,将来の高齢社会の到来を見据え,認知的加齢に関する研究を開始しました.認知的加齢に関する研究も大胆な独創的な切り口で進められることになります.その切り口は,認知科学の枠組みのなかで認知工学の日常生活で用いられる人工物の使いやすさ研究と認知心理学の認知的加齢研究を結びつけた点です.この 2つを結びつけることで,人とモノ相互作用の観点からよりリアルな人の認知の加齢変化の様相を明らかにすることを可能にするだけでなく,超高齢社会で社会的価値もある「誰にとっても使いやすい人工物」に関する知見を社会に提供することを可能にしました.
これらの研究を進めていくなか原田氏は,多くの研究を整理し高齢者が人工物を使用する際に直面する問題について「身体・知覚的機能の低下」「認知的処理の変化」「知識の不足」「動機づけや感情の変化」を取り上げ,これらの問題を組み込んだ「認知的加齢と人 .モノ相互作用の関係モデル( 4層モデル)」を提案されました (原田, 2009;原田・赤津 , 2003).このモデルは,日常を対象としたフィールドや実験室での観察・実験を通して積み上げられた知見をベースにしており 2003年のモデルの提案以降,単に理論的な枠組みにとどまらず検証が進められました.この検証を進めるにあたり,「日常」での研究の必要性を再認識されることになり,筑波大学での新しい取り組みが開始されることになります.
6.「みんラボ」という新たな研究の場の創出
ここまでの原田氏の研究に見られた,日常場面において人の認知の仕組みを明らかにしていくことや,使う人の立場からサービスやプロダクトを観るという特徴は,原田氏が 2011年から筑波大学にて始めたつくば型リビングラボ「みんなの使いやすさラボ(通称:みんラボ)」に集約されていきました.リビングラボとは,市民・行政・企業・大学など多様な立場の人が協働して,実際に人が生きている空間における実践的な活動を通じて,経験的な知見を獲得しようとするアプローチです.みんラボは,特に,市民である高齢者と企業・大学を対象とした使いやすさ研究に着目したリビングラボで,参加している多数の高齢者とともに 4層モデルの妥当性と応用可能性の実証を続けています.
リビングラボは,現在はイノベーションを生み出す共創的なデザイン手法として注目されていますが,その源流には,生きた学習の場を作る教育活動や,ナイサーが主張した生態学的妥当性の高い認知心理学研究,ノーマンらの人間中心のデザインアプローチなどがあります.原田氏は,リビングラボを認知工学・認知心理学的研究の中核的な方法論として確立し,その成果を学術論文だけでなく,地域社会との信頼関係の構築や政策提言にもつなげ,「研究が社会とともにある」ことのモデルケースとして先駆的に推進してきました.みんラボは,高齢者にとっての人工物の使いにくさという課題を,市民とともに科学的に探究するという,日本において画期的な取り組みとなっています.
原田氏のこの研究の特筆すべき点は, 10年以上にわたる継続的なフィールド研究を通じて,「コミュニティで研究する」という方法論を確立・実践してきたことです.研究対象である市民を単なる調査対象ではなく,主体的なパートナーとして位置づけ,研究に能動的に関与してもらう.そのためには,高い倫理性と丁寧なコミュニケーションが求められますが,原田氏はそれを当然の前提として研究を設計・遂行してきました.このようなスタイルは,実験室における統制的な研究では捉えきれなかった認知のリアリティに迫るものであり,社会実装が強く求められる昨今の日本の研究環境の中で,今後の認知科学における重要な方向を示唆していると言えるでしょう.
7.おわりに
原田氏は,人と人工物の相互作用分析にもとづく認知工学を中心として認知科学の発展と後進の育成を進められてきました.特に,原田氏の教え子,共同研究者らが企業等での現場で原田氏のもとで学んだ認知科学の手法をもって様々な社会課題に取り組み,活躍されていることは特記すべきことだと考えます.
こうした原田悦子氏の基礎研究とみんラボでの研究は「生活の中での活動にこそ人間の認知の真実がある」という言葉をまさに体現してきたものだと考えられます.実験室という世界にとどまらず,人工物の使いやすさ,高齢社会という現代社会における切実な課題について,認知科学者として科学的・実践的に取り組み挑戦する姿勢は,認知科学の多くのアカデミア研究者だけでなく現場の研究者に刺激と示唆を与え続けると考えます.
本稿では,あまりお人柄についてのご紹介することはできませんでしたが少しだけご紹介します.原田氏との研究のディスカッションは,ラボミーティングを越えて夜まで続くことが常でした.また,「おいしいものを食べながら考えましょう!」というのが基本方針で,ご自身でおいしそうなお店を見つけて予約されています.そのため,私たちは特にお店の予約をする必要はなく,いつも楽に「美味しい議論」をさせて頂いています.
これまでのご指導に対する深いお礼とともに,今後のご健康と,ますますの研究の発展を祈念して本稿を閉じることとしたいと思います.
文 献
原田悦子 (1987).単語を越える直接プライミング効果:単語対における効果の検討心理学研究 , 58 (5), 302.308. https://doi.org/10.4992/jjpsy.58.302
原田悦子 (1996).潜在記憶研究・意味記憶の枠組みから見た直接プライミング効果風間書房
原田悦子 (1997).人の視点からみた人工物研究日本認知科学会 (編)認知科学モノグラフ 6共立出版
原田悦子 (2009).認知加齢研究はなぜ役に立つのか:認知工学研究と記憶研究の立場から心理学評論 , 52 (3), 383.395. https://doi.org/10.24602/sjpr.52.3_383
原田悦子・赤津裕子 (2003).「使いやすさ」とは何か:高齢社会でのユニバーサルデザインから考える原田悦子 (編)「使いやすさ」の認知科学 (pp. 119.138)共立出版
堀浩一 (1998).書評:原田悦子 (1997).『人の視点からみた人工物研究』 .東京:共立出版認知科学 , 5 (1), 89.91. https://doi.org/10.11225/jcss.5.1_89
(須藤智・新井田統 記)