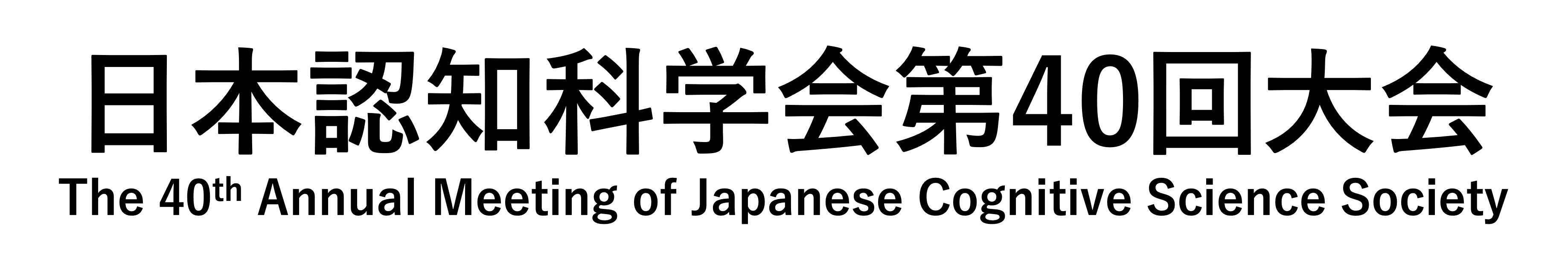各種発表の形式に関して
Free WiFiを提供予定ですが、容量に限りがあるため、口頭発表、オンライン配信予定OS
の発表者に向けて有線LANを提供予定です。有線LANアダプタ等は各自でご用意ください。
口頭発表
- 発表15分(時間厳守)、質疑応答5分です。
- HDMI 出力端子のあるPCを各自でご用意ください。変換アダプター等は各自でご用意ください。
- 発表者はセッション開始の5分前までに、各自PCの接続確認と座長による出席確認をすませてください。
ポスター発表
- ポスターボードのサイズは 幅1120×高1680mmです。
- ポスター会場での受付は不要です。掲示に必要なピン等は、ポスターボードに備え付けてあります。
- 電源コンセントのご用意はありません。あしからずご了承ください。
- ポスターは、各発表日の昼休みに掲示してください。
- 在席責任時間は以下の通りです。
- ポスターセッション1 (9/7):奇数番号 16:00〜17:00 偶数番号 17:00〜18:00
- ポスターセッション2 (9/8):奇数番号 16:30〜17:30 偶数番号 17:30〜18:30
- ポスターセッション3 (9/9):奇数番号 13:30〜14:30 偶数番号 14:30〜15:30
- セッション終了後30分以内に、各自で責任を持ってポスターを撤収し、お持ち帰りください。
オーガナイズドセッション(OS)
- HDMI 出力端子のあるPCを各自でご用意ください。変換アダプター等は各自でご用意ください。
- 特別な機器や設備が必要な場合は、各自でご用意ください。